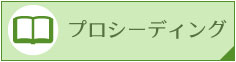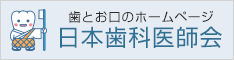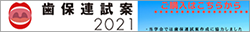『噛んで食べてこそ健康長寿』
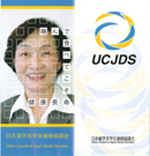
『噛んで食べてこそ健康長寿』
平成17年(2005年)3月発行
噛んで食べてこそ健康長寿
「食べる」ことは、私たちのからだと心の健康を維持するために大切なことであり、人としての尊厳を保ち、「健康長寿」につながります。歳をとって体力が落ち、動くことが不自由になっても、好きなものをおいしく食べ、家族と楽しく語ることができる、そんな老後を誰しも願っているのではないでしょうか。この「食べる」ことに必要なことは、「噛む(
私たちは歯学を研究するなかで、元気で生き生きと一生を過ごす「健康長寿」には、「よく噛んで食べること」が最も重要なことだと考えています。国民の皆さんひとりひとりが生涯にわたって「噛んで食べる」ことができ、健康で長生きができる社会を実現すべく、いろいろな取組を行っていきます。
問題は何か?
- 軟らかいファーストフードの氾濫や安易な栄養補助剤の多用、必ずしも高齢者の各個人の食べる機能を考慮しない病院や要介護施設での食事などは国民の健康を考える上では危機的状況です。これは、「噛んで食べる」ことの重要性を、国民の皆さんに十分理解していただいていないことが原因の一つと考えられます。
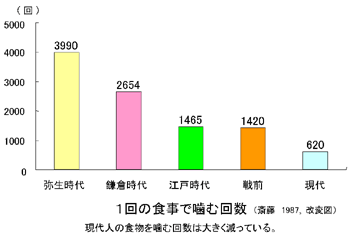
- 現在、生涯にわたる「歯の咬み合わせ」と口の健康を守るための健診は、妊婦、幼児、こども、大人、お年寄りなどに分かれてバラバラに行われていて、一貫性がありません。
- 幼児やこどもの「噛む」能力が低くなって、
顎 の骨や噛む筋肉がうまく成長せず、歯並びが悪くなり、運動能力や学習能力も低下しています。 - 小・中学校で「噛んで食べる」指導と「口の健康を守る」指導が一体となって行われていません。
- 「孤食」や「欠食」など家庭で食卓を囲んで「食べる」ことが十分ではなく、我が国の食文化も守られていません。
- お年寄りの方々が確実に「噛んで食べる」ことができるための、「歯の咬み合わせ」を回復する歯科治療が十分ではありません。
どう解決するか
まず国民の皆さんの理解を深めます
私たちは今まで国民の皆さんに、「噛んで食べる」ことがいかに重要で健康長寿につながるかを、十分にお伝えできていませんでした。このことを深く反省します。今後は、「歯の咬み合わせ」を守って「噛んで食べる」ことに関し、すべての世代に必要な情報を整理して、地域や学校などと協同して、あるいはインターネットを介してお知らせします。
正しい「歯の咬み合わせ」とは
「歯の咬み合わせ」が悪くなると
- 食べにくくなる
- ことばがはっきりしなくなる
- むし歯や歯周病になりやすくなる
顎 の発育が悪くなる顎関節症 になりやすい- 姿勢が悪くなる
- 聴力が低くなる
- 食いしばりや歯ぎしりを起こし、睡眠にも影響することにつながります。
「歯の咬み合わせ」を守って「噛む」ことの大切さとは
- 食べ物本来の味がわかり、おいしく味わえる
- 口や
顎 、顔の発育を促進する - 唾液の分泌を促進する
- 胃腸の働きを促進する
- 栄養素の吸収を助ける
- 肥満を抑制する
- 脳の血流を促進する
- 歯、歯ぐき、歯の周りの骨を強くして、これらに関わる病気を予防する
- 食物中の発がん物質の発がん性を弱める
- 全身の運動能力を向上させる
骨粗鬆症 を予防する- QOL(生活の質)を向上させることなどです。
国民の皆さんは何を実践していただくか
- 家族みんなで「団らん」をしながら食べる
- しっかり噛んで食べる
- 歯と口の健康をしっかり守る
- 悪い歯や咬み合わせはきちんと治療する
「健康長寿」を確保するための歯科医療を進めます
- 生涯の「歯の咬み合わせ」を守る環境の整備に努めます
生涯を通じて「歯の咬み合わせ」を守る歯と口を健康に保つためには、人生の流れに対応した継ぎ目のない健診が必要です。このための歯科医師法および歯科衛生士法における任務規定を整備するとともに、必要な改正を進めます。これによって、むし歯や歯周病の早期発見・早期治療だけではなく、生涯にわたって「歯の咬み合わせ」が守られ、口の健康維持につながり、一生「噛んで食べる」ことができます。 - 口と
顎 の健全な発育と食を育む体制の整備に努めます
学校歯科医や歯科医院の先生方に「噛んで食べる」大切さを改めて教育しなおします。また、管理栄養士の方々とも連携して、栄養指導や「よく噛んで食べる」指導、歯と口の健康指導などを一緒にできる口腔衛生指導教諭(仮称)の育成をはかり、すべての小・中学校に配置します。また、日本学術会議や日本歯科医師会と学校とで作るネットワークを通して、食を育む体制を築きます。 - 全ての介護保険・社会福祉施設へ常勤歯科医師を置くよう努めます
地域の自立しているお年寄りに対する保健師の活動に口の健康教育を組み入れていくよう行政や保健師に働きかけます。また、介護の必要なお年寄りのQOL(生活の質)を向上させるための歯科医療ができるよう、特別養護老人ホームなどの介護保険施設へ常勤歯科医師を配置するよう努めます。さらに、食を通じて保健・医療・福祉を総合的に考えことができる人材を養成し、それらの施設への配置を進めます。
「健康長寿」を確保するための科学と技術を推進します
- 歯学と医学など他領域との連携を強化します
国民の皆さんへ適切な総合的医療を提供するため、医学を含む栄養学・社会福祉学・介護学、他関連学会や食産業界など、関連する他領域と歯学との連携を強化して、「口腔リハビリテーション学」を発展させます。そして、研究から得られた科学的根拠に基づき、健康増進のために必要な具体的な政策の実施を政府に要望します。また、歯学系の各学会は自らの課題としてこの達成に積極的に取り組みます。 - 全国レベルでの大規模な研究を進めます
正しい「歯の咬みあわせ」や「噛んで食べる」ことと、からだの健康、生活習慣病、QOL(生活の質)、ADL(日常の活動性)、栄養などとの因果関係をさらに明らかにするための大規模な研究を進めます。これらの研究で得られた成果は、速やかに歯科治療に応用します。
期待される効果とは
すべての世代が「食べる」ことを通じて「生きる力」を得られるための支援をします。これにより、QOL(生活の質)の向上や人生の終末までの「人間の尊厳」が確立できる高齢社会が実現できます。また、健康増進や介護の予防、介護が重症になることを防ぐことができます。さらに、これらを通じて、医療費や介護費の軽減も可能となり、歯学と歯科医療は国民の皆さんに対する責任を果たしながら、我が国の社会の活力を一層高めることができると考えます。
健康長寿を目指して
ここに書いたことは、我が国科学者の代表機関である日本学術会議と我が国の歯科系66学会が結集して設立した日本歯学系学会協議会が提唱し、実践しようとしているものです。多くの国民の皆さんのご理解とご協力を得て、この提言「噛んで食べてこそ健康長寿」を実現させ、国民の皆さんの幸せに役立ちたいと考えています。
この「噛んで食べてこそ健康長寿」は、平成16年12月16日に公表した報告書です。
詳しい内容は、日本学術会議ホームページをご参照ください。
- 日本学術会議ホームページ
http://www.scj.go.jp/ - 「咬合・咀嚼が創る健康長寿」報告書
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-t1021.pdf