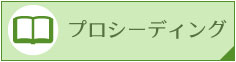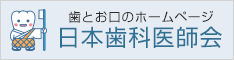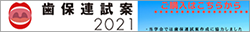役員挨拶
一般社団法人日本歯学系学会協議会 副理事長
片倉 朗(特定非営利活動法人日本口腔科学会)
この度、一般社団法人 日本歯学系学会協議会の副理事長を拝命いたしました片倉朗です。
現在までに日本口腔外科学会や日本老年歯科医学会をはじめとする多くの学会の運営に参加してまいりましたが、今回は日本口腔科学会からの代表として本協議会に参加し副理事長を務めさせて頂くことになりました。日本口腔科学会は日本医学会の中で唯一の歯科系分科会です。日本医学会との情報交換を行うことも私の役目の一つであると認識しています。
本協議会は歯学系の84学会と9つの賛助会員で構成され、歯学の各研究領域を網羅する連絡協議会です。また、歯学のなかで日本学術会議の活動に協力を設立の趣意とする学術団体です。2023年9月に日本学術会議歯学委員会がまとめた「歯学・口腔科学分野の課題と展望」には歯学・口腔科学分野で以下のことを推進する必要性を謳っています。①基礎系・臨床系とともに戦略的な研究支援と人材育成をする、②歯学、口腔科学が包含する領域は、摂食嚥下、栄養、コミュニケーション、呼吸などに関わる機能と形態を 維持、回復することを目的としてウェルビーイングに貢献し多様性と包摂性のある社会の実現する、③ビックデータ解析をもとに生命科学の進展と密接に関わり歯科医療デジタルトランスフォーメーション(DX)と医科歯科連携を促進する。これらを基本に歯学の方向性の将来検討を行い、Science for Societyと分野横断的な観点を以って具体的な政策提言ができる活動の推進に努めてまいります。どうぞよろしくお願い致します。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 常務理事
池邉哲郎((公社)日本口腔外科学会)
この度、日本歯学系学会協議会の常任理事に就任いたしました(公社)日本口腔外科学会の池邉です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
本協議会の目的は、歯学の発展に寄与し、その成果を社会に還元し、国民の健康増進に寄与することですが、それはまさに(公社)日本口腔外科学会の目的でもあります。一方で各歯学系学会の専門分野は様々であり、それぞれの学会がそれぞれの狭い分野の学術成果を公開する構図は、それぞれの学問が縦社会の自己満足で終わる危険性を秘めています。日本歯学系学会協議会の使命は、そのような縦糸に横糸を交差させ、合従して歯学の成果を総合し、それを効果的に社会に還元するとともに学会間の学際的交流を深めることかと思います。また、そこには歯科医師中心の歯科医学の研究者ばかりでなく、歯科衛生士や歯科技工士などを含めた歯学系医療従事者の在り方をも統括し、歯科医療(口腔医療)の将来を学術・社会環境・生涯研修の面から総合的に考究する役割もあるかと思います。
日本口腔外科学会には課題が山積しています。中でも歯学部学生の口腔外科入局者数の減少は今後深刻になろうかと思います。先日或る医科系の学会の理事長がおしゃっていたことですが、その学会では大学に残って専門を研鑽することなく研修修了後すぐに民間の高給の病院に就職する若者が増えていると言って嘆いていました。歯学系学会も同じ問題が生じつつあるかと思われます。特に歯科医療界の喫緊の課題は、人口減少に伴う人材確保とそれに係る人材の地域格差、特に専門医の地域格差(それは国民の健康格差へ直結するかと思います)への対応かと思います。
そのような問題意識を共有しながら、微力ではありますが尽力いたしますので宜しくお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 常務理事
大久保力廣((公社)日本補綴歯科学会、(一社)日本デジタル歯科学会)
この度、日本歯学系学会協議会の常任理事を拝命しました鶴見大学歯学部口腔リハビリテーション補綴学講座の大久保力廣と申します。専門は有床義歯補綴学であり、(公社)日本補綴歯科学会、(公社)日本口腔インプラント学会、(一社)日本接着歯科学会、(一社)日本デジタル歯科学会等を含め、たくさんの学会に所属しております。例え専門は補綴系であっても、最終的な治癒像を高めていくためには、保存、口腔外科、矯正歯科等の関連診療科と密接に連携する必要があります。また、最先端の歯科治療を提供するためには、日本歯科医学会に所属する多くの専門分科会、認定分科会の活動に基づく貴重な情報が不可欠です。さらに、歯科治療をイノベーティブに推進、発展させていくためには、デジタル技術、分子生物学、歯科材料学、医工学、情報学、疫学、老年学、栄養学などの多分野が連携して研究を推進しなければなりません。日本歯学系学会協議会はまさにこうした連携を強化するための存在であり、定款でも、「歯学系学会間の交流を推進し、学術の発展に寄与させ、国民の健康増進に寄与すること」を活動目的と謳っています。私自身も、わが国の歯科治療や歯学研究を牽引するために非常に重要な組織と考え、担当する本協議会の広報活動に尽力したいと思います。
歯科界は現在、沈滞感を拭えず多くの課題に直面しています。「歯科」の社会的プレゼンスを高め、多くの国民に歯科の重要性を再認識していただくためにも、本協議会は加盟学会の連携がより密接になるよう努めたいと思います。
会員の先生方の一層のご支援、ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 常任理事
小見山 道((一社)日本顎関節学会、(一社)日本口腔顔面痛学会)
この度、令和6(2024)年6月11日に開催されました定時社員総会において、一般社団法人日本顎関節学会ならびに一般社団法人日本口腔顔面痛学会からの代表として常任理事に選任されました。何卒よろしくお願い申し上げます。
当法人は定款にありますように、「会員たる歯学系学会間の交流推進を図り、学術の発展に寄与するとともに、会員の研究成果を社会へ還元するための事業を行い、会員たる歯学系学会の社会的認知度の向上並びに国民の健康増進に寄与すること」を目的とし、現在84学会と9つの賛助会員からなるわが国の歯学の各研究領域を網羅する連絡協議会です。したがって、学術会議とも連携し、歯科における専門性の在り方、また歯科が抱える諸課題等に対し、アカデミアの立場から提言を発出するなどの活動を行い、その使命を果たしてきております。今後も、引き続き加盟学会と連携し国民の健康へ貢献するとともに、歯科界のさらなる飛躍に向けて活動いたします。
加入学会の代表として参画している立場としては、学会の社員や会員に対して、本協議会の活動をきちんと説明する責任があります。これまでの協議会の活動については歯科において大変有用であったと考えますが、その活動内容を分かりやすい形で加入学会や関係者に説明するための情報開示が積極的であったとは言い難いと感じておりました。今後は、そのようなことも改善し、加入学会にとって現在当法人が抱える課題と今後の在り方はどうあるべきか、今一度ご意見をいただくことで、その方向性を検討しさらなる改善につなげる所存です。加入学会ならびに賛助会員の皆様におかれましては、今後もご協力のほど、よろしくお願いいたします。
末尾になりますが、加入学会ならびに賛助会員各位の益々のご発展と、本法人に関わる方々のご健勝を祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただきます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 常任理事
沼部 幸博(特定非営利活動法人日本歯周病学会)
この度、日本歯学系学会協議会常任理事(庶務・財務担当)を拝命しました日本歯科大学生命歯学部歯周病学講座の沼部幸博です。現在、特定非営利活動法人日本歯周病学会理事長職も務めています。
本会は2003年(平成15年)に、新世紀において歯学がその存在基盤と主体性を保持して国民の付託に応えるため「社会の要請を適確に捉えて学術研究を推進し、国民の健康と福祉向上に寄与する。」「国民、政府、歯科界に対して積極的な発言と必要な提言を行なう。」この2つの目的で設立されました。
そしてこれまで本会は実際に、「加盟各学会の連携・協力での運営を通し歯学の学術研究に関する諸問題に対する必要な提言。」「日本学術会議での審議等への協力を通じた歯学の学術研究推進と普及。」「国民の健康と福祉向上への貢献。」などの重要な役割を担ってきました。
これらの崇高な設立理念を持つ本会活動にお手伝いができることは大変光栄であるとともに、責任の重さを実感しています。
とくに庶務、財務関連の仕事は本会の円滑な活動推進における重要な歯車の一つです。本年度の事業計画においても大切な課題がいくつか掲げられており、今井裕理事長のもと、与えられた使命を全うする所存です。
本会活動へのご指導、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 常務理事
山本一世(一般社団法人日本歯科審美学会)
この度、前期の理事から引き続き本協議会常任理事を拝命いたしました、日本歯科審美学会の山本一世です。担当は前期と同じ企画担当を仰せつかっております。同じく企画担当理事の天野敦雄先生、上野俊明先生と力を合わせ、本協議会の発展に力を尽くして参りたいと念願しております。
3年以上という想定外の長期に渡った新型コロナウイルス感染症が2023年5月に2類相当から5類に引き下げられ、様々な社会活動が再び活発化してきました。コロナ禍中は「マスク美人」なる言葉も生まれましたが、“明眸皓歯”の四文字熟語が示すとおり、口元は目元と並んで顔貌を形づくる二大要素であり、コミュニケーションの上でも“表情”はなくてはならないものです。しかしながら、日本歯科医師会が2022年に一般人を対象として行った「歯科医療に関する生活者意識調査」によると、多くの人々が「健康のためにできるだけ自分の歯を残したい」「健康を維持するうえで、歯や口の健康は欠かせない」「歯や口の健康を大切にしている」と回答しているものの、歯科医療機関で定期チェックを受けている人は半数以下という結果が得られています。また厚生労働省からは令和4年歯科疾患実態調査の結果が公表され、わが国の8020達成者がさらに増加していることが示されていますが、このことは同時に歯科医療者が、高齢者で頻繁にみられる根面齲蝕やtooth wear への対応にますます迫られること、そして若い時期からの口腔健康管理が今後ますます重要となることを示しています。そこで、超高齢社会のわが国における歯科医療の重要性に鑑み、今期も本協議会設立の趣意である「歯学の学術研究の推進と普及を図り、もって国民の健康と福祉の向上に貢献する」ことを目指し、できる限り有益な情報発信を心掛ける所存ですので、ご支援・ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 理事
天野敦雄(一般社団法人日本口腔衛生学会)
このたび理事を仰せつかりました日本口腔衛生学会の天野敦雄でございます。2024年4月より大阪大学名誉教授/特任教授(予防歯科学講座)となっております。本協議会が目指す「歯学の学術研究の推進と普及」、「国民の健康と福祉の向上」に微力ではございますがお役にたてればと思っております。何卒宜しくお願い致します。
歯学系学会連絡協議会の設立は2003年。奇しくも私が大阪大学教授となった2000年と同時期です。以来の四半世紀、日本のアカデミアは大きな変革の波に洗われています。化石資源に乏しい日本は、知的資産を枯れることのない資源とすることを目指しています。大学院重点化、国立大学法人化、選択と集中、世界大学ランキング、指定国立大学、国際卓越研究大学といった言葉が、アカデミアの環境変化を如実に示しています。
知の本質だけを見ていた時代は過去のものとなりました。「知の創造と活用の好循環によるイノベーションの創出」、「産学官の持続的・発展的なパートナーシップの確立」が令和のアカデミアの道の先です。確かな羅針盤を手にするために、歯科の学府の総力が必要です。歯科界のさらなる飛躍に向けた日本歯学系学会協議会の活動に、歯科系学会各位のご理解とご協力をお願い致します。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 理事
井上美津子(一般社団法人ジャパンオーラルヘルス学会)
このたび、2024-2025年度の本協議会の理事を務めさせていただくことになりました 昭和大学歯学部小児成育歯科学講座の井上美津子と申します。 選出母体となる一般社団法人ジャパンオーラルヘルス学会は、本協議会の監事でもある山根源之理事長のもと、旧日本歯科人間ドック学会から学会名を変更し、より幅広く国民の口腔と全身の健康維持・増進に貢献すべく、活動を行っています。また学会認定の歯科医師ばかりでなく、ドックコーディネーターや予防歯科管理を行う認定歯科衛生士の養成にも力を注いでおります。
私は、昭和大学の臨床講座では小児歯科分野を担当しており、小児・障害児の歯科医療や、小児保健・母子保健に関する調査研究等を主体に行ってまいりました。
医療ばかりでなく、保健の分野の方々との交流を深めたり、歯学部の教育委員長として学生教育の現場での研鑽もさせていただきました。 また昭和大学では、宮崎 隆先生(元学部長)が本協議会の理事長だった時代に、総会や講演会、シンポジウムなどが昭和大学で開催されることが多かったため、在職中はいろいろと参加させていただいておりました。
今回 理事となり、改めて定款などを確認させていただきました。 本協議会の設立からの活動などを自分の中に位置づけ、妊娠期も含めた小児期から高齢期までのライフコースにおける国民の健康に寄与できるような歯科医学と歯科臨床の発展に、本協議会が貢献できるよう、少しでもお手伝いができればと考えております。 何卒よろしくお願いいたします。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 理事
上野 俊明(一般社団法人日本スポーツ歯科医学会)
このたび一般社団法人日本歯学系学会協議会の理事職を拝命いたしました、明海大学の上野俊明と申します。私は現在、選出母体である一般社団法人日本スポーツ歯科医学会において、総務理事および医療保険担当理事を務めさせていただいております。また一般社団法人日本外傷歯学会理事のほか、公益財団法人日本スポーツ協会スポーツ医・科学専門委員会委員やスポーツ庁関連のスポーツ事故防止対策協議会委員なども務めさせていただいております。そうした経験などを生かしながら、本協議会が目指している歯学系学会間の交流の推進や研究成果の社会還元を促進する事業に取り組み、歯学系学会の社会的認知度の向上や国民の健康増進に寄与する活動を推進するため、微力ながら尽力したいと思っております。今期ですが、今井裕理事長のご指導のもとで、企画を担当させていただくこととなりました。主任である山本一世常任理事および天野敦雄理事とともに、シンポジウムおよび講演会等の開催や日本学術会議ほかの関連団体とシンポジウム・講演会等の共催、会員学会主催の学術講演会等への後援活動を中心に、職責を果たしてまいります。なにぶん浅学の身ですので、執行部役員の先生方にはもちろんのこと、会員学会および賛助会員の皆様方にもご指導ご鞭撻を賜りたく、心よりお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 理事
北村和夫(一般社団法人日本顕微鏡歯科学会)
日本歯科大学附属病院総合診療科1教授の北村和夫と申します。専門は歯内療法ですが、一般社団法人日本顕微鏡歯科学会の前理事長を拝命しておりましたため、同学会を選出母体として日本歯学系学会協議会(歯学協)の理事に選出されました。令和6年度定時社員総会にて庶務・財務を担当することになりました。
日本顕微鏡歯科学会は、2004年に研究会として発足し、2006年から学会として活動を始めました。当初はオンラインジャーナルのみで論文等の対応をしていましたが、現在、学会誌として The International Journal of Microdentistry(英文誌)を年2回発刊しております。また、マイクロデンティストリーYEAR BOOK も2011年から毎年発刊しております。学術大会は、年1回開催していますが、近年、ハイブリッド開催するようになったこともあり、参加人数は1,000 名を超える等、年々成長している学会です。また、症例検討会として、若い先生方の発表の場としてシーズンズセミナーを、歯科衛生士の研鑽の機会として、歯科衛生士セミナーを毎年開催しております。若い会員が多い学会なので毎回熱気あふれるディスカッションが行われ、参加予定定員数をオーバーすることも多く、対応に苦慮しております。また、歯科用手術顕微鏡を使用した歯内療法が保険改正の度に適用範囲を拡大している関係もあり、現在の会員数は正会員(歯科医師、医師等)、準会員(歯科衛生士、歯科技工士等)、 法人会員あわせて2,000を超えています。 私は、現在、(一社)日本歯科保存学会 理事、(一社)ジャパンオーラルヘルス学会 理事、日本歯科大学歯学会 理事などを務めさせていただいております。歯学協理事就任は初めての事で至らない点もあるかとは存じますが、大任をお受けしたからには、誠心誠意、歯学系学会協議会の発展のため職務に尽力いたす覚悟でございます。なにとぞ、前任者同様の皆さまのご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 理事
里村一人(一般社団法人日本口腔内科学会)
このたび、今井 裕理事長のご推薦により、日本歯学系学会協議会の理事(調査担当)を拝命いたしました(一社)日本口腔内科学会の里村一人(鶴見大学歯学部口腔内科学講座)と申します。日本口腔内科学会は1991年に口腔粘膜疾患研究会として発足し、1995年に日本口腔粘膜学会となり、さらに2011年に学会名称を日本口腔内科学会に改めるとともに、2014年には任意団体から一般社団法人へと移行しました。また2021年には日本歯科医学会の認定分科会、さらに2022年には日本歯科専門医機構の社員学会となり、2024年7月31日現在、会員数は936名となっています。超高齢社会であるわが国においては、粘膜疾患や口腔乾燥症、口腔心身症などの内科的治療が主体となる疾患に対しては、相当数の患者が潜在的に存在していると推定されるにもかかわらず、病因・病態の解明、適切な診断法や治療法の確立が進んでいません。本学会は、このような疾患の病因・病態の解明を目指すとともに、疾患の診断・治療・管理を行う、さらにはより低侵襲な診断・治療を実践する診療分野の確立を目指して活動しています。
一方、私の経歴ですが、1988年に徳島大学歯学部を卒業し、大学院で口腔外科学を専攻しました。その後、母校の口腔外科学第一講座(当時)に在籍し、1995年から3年間Visiting fellowとして米国国立衛生研究所(NIH、NIDCR)に在籍、帰国後母校に奉職した後、2009年から鶴見大学歯学部で口腔内科学講座を担当しています。
私が歯学系学会協議会の理事を拝命するのは今回が初めてですが、任期中、協議会の発展、ひいてはわが国における口腔医学・口腔医療の発展とその成果の国民医療への還元に向けて精一杯努めさせていただく所存ですので、関係の皆様にはご指導、ご鞭撻いただきますようお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 理事
林 美加子(特定非営利活動法人日本歯科保存学会)
日本歯科保存学会理事長として理事を拝命いたしました、大阪大学 林美加子です。
この日本歯学系学会協議会をとおして、歯科・口腔科学が、社会の要請を踏まえた学術研究を推進するために、生命科学領域の学術のみならず、変遷する倫理や法政等についても、学会横断的に意思疎通を図ることは極めて重要であると思います。
この数年来、歯科・口腔科学領域の研究は、ゲノム編集技術、バイオインフォマティクス、ビッグデータおよびAIなど、かつてないスピードで進化してきました。本協議会は、グローバル世界でダイナミックに融合・進化を繰り返す最先端の科学技術を共有できる、貴重なプラットフォームであることに間違いありません。
また、超高齢社会の中で、医科と歯科の連携が、学会のみならず社会的にも注目されています。本協議会が、歯科を取巻く情勢を多様な観点から俯瞰しつつ、学会横断的に議論を深めることによって、社会の期待に応える提言を発信することも第一義的な目的であります。
一方、社会科学的な共通認識を学会間で構築することも、意義あるアプローチではないかと思います。例えば、急速に進化を遂げるAIの世界では、データセットの巨大化と機械学習の進展で、現実と虚実の境界が曖昧になりつつあります。このような新領域に関する理解を深め、歯科・口腔科学領域に特徴的な倫理や法政に係る共通認識を構築することも、この協議会ならではの役割ではないかと考えます。
協議会の設立以来、先輩方が築いてこられた、歯学の各研究領域を網羅する連絡組織としての役割を理解した上で、変革を遂げる生命科学領域の学術を歯学領域に反映させる使命を果たしてまいりたく思います。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 理事
細川隆司(公益社団法人 日本口腔インプラント学会)
このたび、日本歯学系学会協議会(CJDSS)の理事を拝命致しました日本口腔インプラント学会理事長の細川隆司より、就任にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。
日本歯学系学会協議会は、歯学・歯科医療に関連する学術団体が結集し、学術研究の推進、教育の充実、政策提言を行うことで、国民の健康増進と社会貢献を果たすことを目指しており、歯科医学界において極めて重要な役割を担っています。近年、超高齢社会の進展に伴い、口腔の健康が全身の健康に密接に関わることが広く認識されるようになり、歯科医療の重要性がますます高まっています。こうした時代の変化に対応し、歯科医療の価値を社会に正しく伝え、新たな治療法の開発につながる質の高い研究の推進と科学的根拠に基づく質の高い医療を提供できるよう、学会間の連携をさらに強化していくことが求められています。
私が理事長を務める日本口腔インプラント学会は、口腔インプラント治療の学術的発展と臨床技術の向上を目指し、研究の推進、専門医制度の確立、安全管理の強化など、多岐にわたる活動を展開しています。本協議会の活動を通じて、他の学会と連携しながら様々な学会活動を推進し、歯科医療全体の発展に貢献していきたいと考えております。
皆様のご支援とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 監事
末瀬一彦(公益社団法人日本歯科医師会)
このたび、(公社)日本歯科医師会からの出向によりまして、本協議会「監事」を務めさせていただきます。浅学非才ではありますが、本協議会の趣意に従い、職務に精励させていただきます。
私は、これまで日本デジタル歯科学会・日本歯科技工学会から立候補し、常任理事を務めさせていただいてまいりました。多くの役員の先生方のご指導を賜りながら、調査研究のミッションを務めさせていただきましたが、今回は、立場が変わり、さらに重責を担わせていただくことになりました。
本協議会は、設立趣意書にあるように「社会の要請を適確に捉えて学術研究を推進し、国民の健康と福祉の向上に寄与するとともに、国民、政府、歯科界に対して積極的な発言と必要な提言を行わなければならないために、歯学の研究領域を網羅した歯学系全学会の連絡組織を設立して、研究者相互の情報交換と意思疎通を緊密にする必要」があります。したがって、(公社)日本歯科医師会傘下の日本歯科医学会とは異なり、日本の多くの歯科系学会が集い、独自性をもった活動が行われています。専門学会だけでなく、大学の学会や歯科技工学会、歯科衛生学会なども加盟され、幅広く、歯科医療発展のための活動が行われています。
本協議会は2003年に設立され、20年を超える歴史が刻まれてまいりました。最近ではコロナ禍の影響で協議会活動も低調でしたが、これからは設立時の目的である「歯学の学術研究に関する諸問題に対して協議し必要な提言を行うとともに、日本学術会議における審議等にも積極的に協力することによって歯学の学術研究の推進と普及を図り、もって国民の健康と福祉の向上に貢献すること」を再確認するとともに、加盟学会の強い結束のもと、日本の歯科界発展のために前進していくことを願っています。「監事」として少しでもお役に立てるように務めさせていただきます。
一般社団法人日本歯学系学会協議会 監事
山根源之(東京歯科大学名誉教授)
本年4月から今井 裕理事長のもとで私は引き続き監事を務めています。私は歯学協設立の時から関わり、発足から現在までの足跡を知る1人です。2003年9月16日に日本歯学系学会連絡協議会(歯学協)が設立され、同年11月19日に歯学協第1回理事会が日本学術会議の会議室にて開催され、設立に協力戴いた総務省日本学術会議改革法案準備室総括副主幹の鏡味裕介氏も出席されました。当時、歯科の学術団体から国に対して直接政策提言を行うことは難しく、学術会議を通して提言することが検討されました。学術会議と関係が深い学術会議研究連絡会議(研連)と日本歯科医学会、日本歯科医師会からの代表者が集まり歯学協を組織しました。大学所属の学会や歯科衛生学会、歯科技工学会にも声をかけ、発足時60学会を超えました。しかし、とりまとめと方向性の確立は大変な作業でした。赤川安正初代会長(当時の代表名)時代の2007年4月には有限責任中間法人になり「日本歯学系学会協議会(歯学協)」と改称し、代表は理事長になりました。2008年には一般社団法人格を取得しました。私は創設時から常務理事として、2006年からは副理事長として会務を務めました。赤川理事長は日本の歯科界は目線を広く国民に向け、国家として利するものでなければいけないと主張され、社会に向け作製された多くのリーフレットはまさにその理を実践されたものでした。
また2009年には歯学協が主導し、会員学会からの委員で構成した『歯学系学会社会保険委員会連合(歯保連)』が設立され、歯学協とは独立した適正医療保険制度のための組織が作られました。
2010年4月に私は2代目理事長として、2014年まで務めました。2014年からは3代目宮崎 隆理事長が就任され、その2期目の2016年から監事に就任しました。それ以来、羽村 章前理事長、今井 裕現理事長のもとで監事を務めてまいりました。大きくなった歯学協が初心を忘れることなく、定款に沿った活動を展開できるか監事として見守っていきたいと思います。